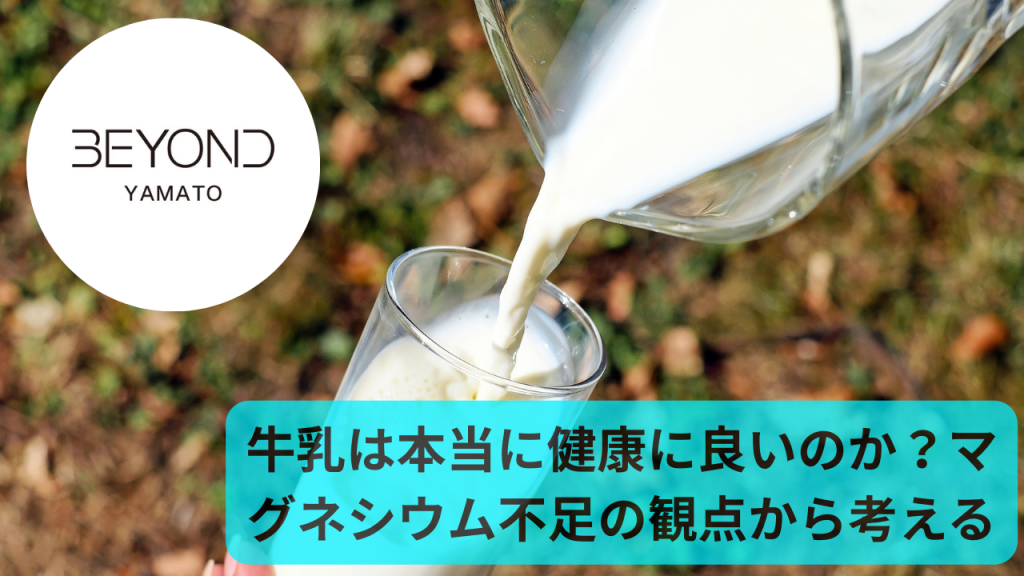
近年、栄養学的な観点から「牛乳は健康にとって必ずしも良いとは限らない」という意見が目立つようになっています。
中でも注目すべき指摘のひとつが、「牛乳に含まれるカルシウムとマグネシウムのバランスの悪さ」です。
この記事では、マグネシウムの重要性、牛乳との関係、健康への影響について詳しく掘り下げていきます。

🔸南部良介 Ryosuke Nanbu
🔸九州男児 福岡出身
🔸ラグビー、水泳、サッカー、陸上
🔸大会歴
・2019 SOUTH JAPAN CHAMPIONSHIPS
Men’s Physique novice -170cm 2th🥈
・2024APF GUARDNER BELT CUP 2024Men’s Physique First timer 3th🥉
目次
カルシウムは、骨や歯の形成に欠かせない栄養素であり、私たちの体内で最も多く存在するミネラルです。
一方、マグネシウムは、体内で約25gほど存在し、カルシウムと共に働く非常に重要なミネラルです。
・カルシウムの吸収と代謝を調整
・筋肉の収縮とリラックスの調整
・神経伝達のバランスを保つ
・心臓のリズム維持
・血糖や血圧の調整
・エネルギー代謝の補助(300以上の酵素に関与)
こうして見ると、マグネシウムは健康維持にとって非常に多面的な働きをしており、単なる“補助ミネラル”ではありません。
むしろ「体内のバランスを保つ陰の主役」と言ってもよい存在なのです。
栄養学の世界では、カルシウムとマグネシウムの理想的な摂取比率は『2:1』とされています。
つまり、カルシウムを600mg摂取するなら、マグネシウムは300〜400mgほどが理想とされます。
このバランスが崩れてしまうと、たとえカルシウムを十分に摂取していても、体内で正しく利用されないばかりか、逆にカルシウム過多の悪影響が現れることすらあります。
・骨に蓄積されず血管や関節に沈着する(動脈硬化・関節炎)
・筋肉のけいれん・神経の過敏
・頭痛や不眠、精神的なイライラ
・心臓のリズム異常や高血圧
さて、問題の牛乳です。
一般的な100mlの牛乳に含まれるカルシウムはおよそ110mg、マグネシウムは10mg前後です。
これは「11:1」という極端な比率で、理想とされる「2:1」からは大きく外れています。
つまり、牛乳ばかりを飲んでカルシウムを摂取していると、マグネシウム不足に拍車がかかってしまう可能性があるのです。
・足がつりやすくなる(筋肉の過剰収縮)
・不眠や神経過敏
・イライラや集中力の低下
・便秘や血圧の変動
・骨折のリスク(骨がスカスカになる)
「カルシウムを摂っていれば骨は強くなる」というのは大きな誤解で、カルシウムだけでなく、マグネシウム、ビタミンD、ビタミンKなどの協調作用によってはじめて骨の健康は保たれます。

牛乳を完全に否定する必要はありませんが、摂取する際には他の栄養素とのバランスを意識することが重要です。
特に、以下のような食品と組み合わせると良いでしょう。
・ナッツ類(アーモンド、カシューナッツ)
・海藻類(ひじき、わかめ)
・緑黄色野菜(ほうれん草、ブロッコリー)
・豆類(納豆、豆腐)
・バナナやアボカド(カリウムとマグネシウムも豊富)
近年では、アーモンドミルクやオーツミルク、豆乳など、牛乳の代替として栄養バランスの優れた飲料も普及しています。
これらはマグネシウムやビタミンEが豊富なものも多く、乳糖不耐症の方にもおすすめです。
牛乳は確かにカルシウムを多く含んだ飲み物です。
しかし、そのカルシウムの働きを最大限に生かすためには、マグネシウムという“パートナー”の存在が欠かせません。
マグネシウムが不足したまま牛乳を過剰に摂取すると、かえって健康を害する可能性があることを、私たちは知っておくべきです。
これからの時代は「何を摂るか」だけでなく、「どのように摂るか」が問われる時代です。
栄養素のバランスを意識して、自分に合った健康習慣を見つけていきましょう。

・ダイエットしたい
・今年こそは結果を出したい
・産後太り解消したい
・姿勢を良くして、服を着こなしたい
・自分に合ったジムがわからない
・「興味はあるけど、本当に続けられるか不安…」
そんな方こそ、まずは体験トレーニングから始めてみませんか?
BEYOND大和店では無料体験トレーニングを実施しております。
専門トレーナーによるカウンセリング付きで、あなたの体質や目標に合ったプランをご提案します。
👇今すぐ体験を申し込む👇
あなたの「変わりたい」を、今日ここからスタートしませんか!
パーソナルジムBEYOND大和店のカウンセリングを通じて、
目標設定とニーズの明確化、健康状態とリスク評価、モチベーションとメンタルサポート、
進捗モニタリングと調整、カスタマーサービスと満足度の向上といった多くのメリットを提供します。
カウンセリングの重要性を認識し、パーソナルジムBEYOND大和店のカウンセリングを活用して、
個々の目標に向かって効果的に取り組みましょう!
目標達成はもちろんのこと、期間や予算そしてペースなどによって
既存のプランからの組み合わせなども可能です!お気軽にご相談くださいませ
【 BEYOND(ビヨンド)大和店 】
📮 住所 👟
神奈川県大和市大和南一丁目 3番3号 スズビル4F
👇LINE追加はこちらから👇
■大和駅アクセス
🚃相鉄線
🚃小田急線
大和駅から徒歩1分🚶♀️